af Magazine
〜旭硝子財団 地球環境マガジン〜
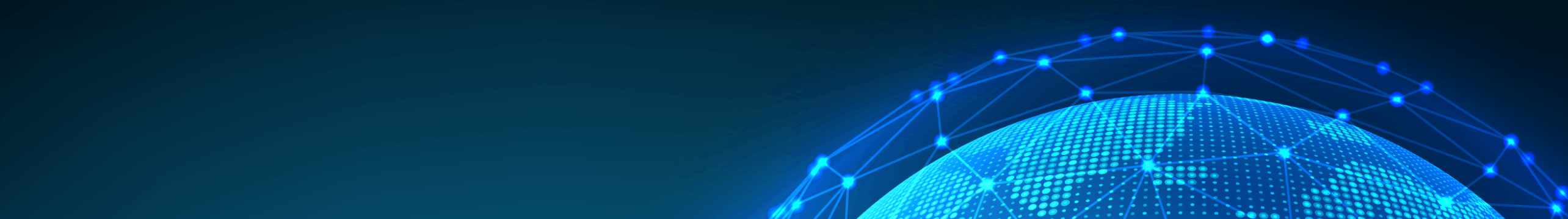

震災復興の経験が教える、海からはじまる持続可能性
- 助成期間:2017年4月〜2019年3月
- 採択テーマ:震災復興経験からのレジリアンスある水産業構築にむけた政策探求気仙沼延縄漁業を起点とした沿岸コミュニティ再構築事例分析
岩手大学の石村学志准教授は、どのように漁業資源を利用すれば持続的な漁業システムを作ることができるのか、数理分析を用いて研究してきました。とくに気仙沼の漁業者の方々に対しては10年以上にわたり、分析に基づいた経営改善提案を通じて、震災からの復興を支援してきました。今、気仙沼の震災復興経験は、海の持続可能性を示唆する事例として世界に認められ、さらなる研究へと発展しています。
復興プロセスから持続可能な漁業のあり方を探る

近年、世界の重要なテーマとなっている、「海の持続可能性」。世界的に漁獲量が減少する一方で、新興国の経済発展などを背景に全体の水産消費量は増加しており、各国が水産資源を争奪する状況になっています。日本国内では、特定魚種の不漁や漁業者の後継者不足などの課題も指摘されています。大学院在学中から水産資源管理を専門とする岩手大学の石村准教授は、数理分析という手法によって、持続可能な資源利用のシステムをつくるべく研究を続けてきました。
石村准教授が10年以上研究パートナーとしてチームを組んでいるのが、宮城県気仙沼港に水揚げをする「気仙沼近海はえ縄漁」の船団です。助成研究のテーマとなったのは、本船団が東日本大震災から復興したプロセスの分析により、漁業の持続可能性を探ることでした。
「本船団は、震災後の困難な状況から再興を遂げました。しかも震災前に比べると、持続可能性の高い経営へと改善しています。その要因はどこにあったのか調べることで、リスクに強いレジリアンス(回復力)のある漁業のあり方を探り、どんな政策を取り得るか考えることが研究の目的でした」と石村准教授は振り返ります。
気仙沼近海はえ縄漁業船団は、この地域において単なる一事業者ではなく、地域コミュニティにとって非常に重要な存在でした。船団が漁獲していたのは、主にメカジキとヨシキリザメ。気仙沼地域にとって、サメ加工業は多くの雇用を支える、地域の主要産業です。この船団が水揚げするヨシキリザメは、ほぼ100%が地域の加工会社に買い取られ、地域ではんぺんの材料などに加工されていました。
気仙沼漁港に水揚げする船のなかには、地域外の船も多くあります。しかし、この船団はほとんどの関係者が気仙沼の住民。一年を通じて安定的に大きな水揚げ量のある、気仙沼という地域にとって重要な船団でした。
「この船団の復興なくして、地域の復興はあり得ませんでした。私たちの研究は、漁業という産業だけなく、沿岸コミュニティの再興にも主眼を置いていました。レジリアンスのある持続可能な沿岸地域をつくるための、研究と実践だったといえると思います」(石村准教授)
貴重な漁獲データを持つ「気仙沼近海はえ縄漁業船団」との出会い

石村准教授と船団の出会いは、震災以前の2008年に遡ります。経営の悪化していた船団をサポートするため、研究機関から当時カナダの大学院にいた石村准教授が派遣されたのです。
「この船団は、世界でも類をみない、貴重なデータを持っていたんです。海にどれくらいの魚がいるのか? これは水産資源管理を考えるための最初の問いと言えますが、答えを導き出すのはとても大変です。現状、水産資源量の推定は、商業漁業からのデータに依存しています。気仙沼の船団は、1980年代からの北太平洋の水産資源のデータを唯一持っている重要な漁業者たちでした。 漁業制度上、漁獲したものを詳細に記録していたんです」と石村准教授。調査を行って経営改善に貢献することが、数理分析を行う研究者としての責務でした。
2011年、東日本大震災が発生したのは、経営改善にむけてプロジェクトを進行している最中のこと。気仙沼市は津波により大きな被害を受け、港では大規模な火災も発生。船の多くは外洋にいたため助かりましたが、港にあった2隻は完全に焼けてしまいました。すぐに現地を訪れた石村准教授は、被災状況を前に決意を新たにしたといいます。
「私は、水産学は実学だと考えています。つまり、産業を支えていくための学問です。リアルタイムで現状に関わり、より良い方向にどう変えていくのか。水産学を学ぶものとして、震災からの復興を支えることは当然の使命でした」(石村准教授)
石村准教授はまず、学生とふたりで、船主や船頭へのインタビューを行いました。もうおしまいだ、再び漁業を復興するのは難しい......そんな雰囲気が漂い、実際にそう口にする人もいました。しかしインタビューの過程で、ある思いがけないことが起こったと言います。
「いくら水揚げがあったら息子や孫に漁業を継ぎたいと思いますか。彼らに、そんな問いを投げかけました。ほとんどの方が、考えた末に1隻あたり水揚げ高2億円と答えました。充分に生活できて、船を作り替える資金も確保できる金額がそれくらいだったんですね。するとおもしろいことに、その答えを口にしてから、もうだめだと言っていた人たちの目に光が戻りはじめたんです。ゴールの達成にむけて、人材や資材をどう配置していくか、戦略を立てることができるようになったんです」
人、家、職場・・・多くが流されてしまった喪失感のなかで、「水揚げ高2億円」という具体的な数値目標は、人々の気持ちを前に向かせる原動力になっていきました。石村准教授は「分析して戦略を示すだけでなく、我々が漁業者に係わることで潜在的なビジョンを引き出し、モチベーションを保つことになる。それを学んだ最初の経験でした。月日を経て、問いの力の大きさを実感しています」と話します。
理論に基づく航海日数の改善と協働が、復興の鍵に

復興へと進みはじめた船団をサポートするため、石村准教授が行ったのは「生物経済モデル」の分析です。一定数の魚を残して資源回復をはかる生物モデルと、市場における漁獲量と価格の相関関係を分析した価格モデルを組み合わせることで、適正な漁獲量と適正な価格を算出しました。その結果、一度出航して港に帰るまでの航海日数を震災前の「43日」から「25日」にすることで、資源管理しながら利益が最大化することがわかりました。
「船頭さんの立場としては、1回の航海でできるだけたくさん漁獲し、船を満載にして帰ってきたいと思うわけです。しかし、航海日数が長くなると費用がかさみ、魚の鮮度も落ち、量が多すぎると取引価格も下がってしまう。少なめにとってこまめに帰ってくることで利益が大幅に改善しました。災害時に柔軟な対応をしやすいことや、船員の体調管理や福利厚生の側面からもメリットがありました」(石村准教授)
航海期間短縮に加え、船団が取り入れたシステムが「共同操業」です。それまでは個々の船がそれぞれの判断で港に帰っていたため、水揚げのタイミングが被ることもしばしば。市場に魚が溢れ、価格が下がることも多々ありました。そこで、みんなで情報を共有し、1日入港するのは1隻までとする入港規制を行うことにしました。震災後、1キロ700〜800円だったメカジキの価格は、1キロ1000円を超えるまでに向上。適正量に加えて、鮮度が向上したことで商品力が高まり、刺身などの需要を生み出したことが要因でした。
「漁業者だけでなく、地域コミュニティそのものが、復興に向けて協力し、変化に対応していきました。加工・流通の努力によって、鮮度よく水揚げして鮮度よく届ける体制が整ったのです。広域でメカジキを刺身で提供できるようになり、需要増につながりました」(石村准教授)
メカジキだけでなく、ヨシキリザメの価格も震災直後の2倍まで向上し、震災前には採算ラインを割っていた水揚げ高は、2016年には平均約2億円を達成※。復興を経て持続的漁業を行える経営体制を確立するに至りました。
※2020年、2021年現在は、新型コロナウイルス感染拡大による経済的影響を受け水揚げ高が減少。おおよその12月月間平均を比較すると、2019年1キロ1000円ほどだったメカジキの価格は1キロ500〜600円ほどに下落した
国際的にも評価される漁業へ。持続可能性の針路は海にある

2018年10月、協働操業のその先へ、船団は一歩を踏み出しました。「気仙沼かなえ漁業株式会社」というひとつの会社となることを決意したのです。同年には新船「かなえ丸」が完成。復興と新しいスタートを象徴する存在として、気仙沼漁港で進水しました。
未来に向けて、かなえ漁業株式会社を含む気仙沼の漁協や石村准教授の研究室などがチームを組み、続けている挑戦があります。それは、メカジキ・ヨシキリザメ漁のMSC認証(海のエコラベル)の取得です。震災以前から、サメ漁に対する国際評価は大きな課題でした。世界ではフカヒレのためにヒレだけを取って身を捨てる漁業が問題になっており、気仙沼は世界で唯一その手法を行わない産地であるにも関わらず、偏見の目にさらされてきました。漁獲量も多くはなく、持続可能な漁業を行っている気仙沼の実態を、世界にはっきりと主張していくことが必要だと石村准教授は言います。
一方で、気仙沼はえ縄漁業の復興事例は、国内外の海洋研究者たちから大きな注目を集めています。気仙沼沿岸地域の復興に向けたこの10年の研究と取り組みが評価され、石村准教授はアメリカのピュー(Pew)財団のフェローに選ばれました。さらに、内閣府の主導するムーンショット型研究開発制度の目標候補にも選ばれ、気仙沼の事例等をベースに、新しい海洋国家としての日本の確立と飢餓と貧困を海から解決していく研究も進めています※。
「気仙沼の事例から見えてきたのは、水産資源や漁業の持続可能性は、地域コミュニティの持続可能性であるということです。漁業者、加工者、そこで雇用されるたくさんのひとたちが一体となって産業が垂直協力していくことで、透明性と持続性が高まることが証明されました。今、この経験を大きく発展させ、海に囲まれた日本の持続可能性を、海を起点に考えていこうとしています」
水産資源の持続的な使用は、食料問題と貧困問題の解決につながる、と石村准教授。最後に、読者や学生へのメッセージとして、これまで多くの人が無意識に関わってきた海という存在を、もう一度見つめ直してほしいと語ります。
「生活者の視点で、海を持続的に使うためにはどうしたらいいのかを考え、海と関わっていくこと。思いをめぐらせ、行動を変えることが未来につながります。今何をすべきかという問いから、はじめてほしいと思います」
※ムーンショット・ミレニア・プログラム『地域海洋資源が⽀える社会経済の多極化による新海洋国家=日本実現が導く、飢餓と貧困なき全球への始動』(略称WeON=Wealth of Ocean Nation)ホームページ:https://weon.jp/
Profile
石村学志(いしむら がくし)
岩手大学 農学部 資源経済・政策と数理資源研究室 准教授
北海道大学水産学部卒業。ワシントン大学大学院、ノルウエー経済高等学院を経て2010年にブリティッシュコロンビア大学大学院にて国際共有資源の経済研究でPh.D.を取得。2015年に岩手大学に着任し、数理分析により、どのように社会が漁業資源を利用しているのか、どのように利用すれば持続的な漁業システムが構築できるかを、国内外の多様な漁業を事例に研究。水産学を実学としてとらえ、数理や経済分析を応用した政策研究を行なう。

