af Magazine
〜旭硝子財団 地球環境マガジン〜
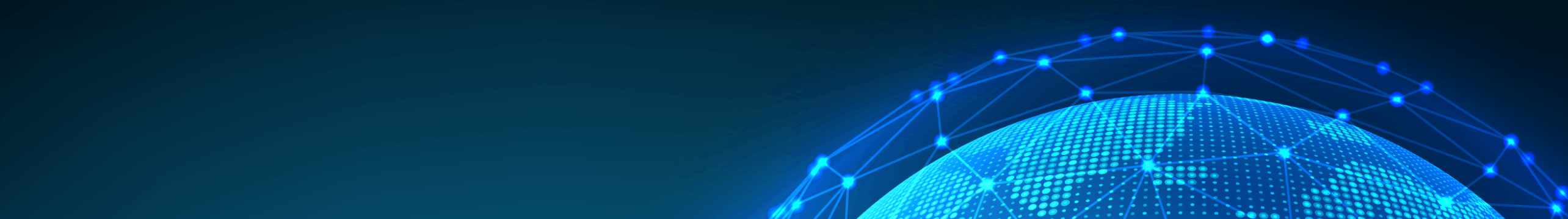

なぜ気候災害は日本にとってそれほどリスクなのか? 専門家が指摘する「3つの問題」

2023年6月14日、環境問題の解決に向けて貢献した個人や団体を表彰する「ブループラネット賞」(主催・旭硝子財団)第32回受賞者が発表された。
受賞者の一人、ベルギーのルーヴァン・カトリック大学災害疫学研究センター(CRED)所長、米国ジョンズ・ホプキンス大学ブルームバーグ公衆衛生大学院 人道的健康センター上級研究員のデバラティ・グハ=サピール教授(以下、グハ=サピール教授)は、数ある自然災害の中でも特に気候災害の増加と被害の深刻化、そして充実したデータの不足に警鐘を鳴らす。
大規模災害のグローバルなデータベース「EM-DAT(Emergency Events Database)」を立ち上げ、開発を主導してきたグハ=サピール教授に、地球規模の災害状況の変化やデータベースの作成を通じて分かってきたことを聞いた。

本人提供
EM-DATは、世界184カ国を対象として、1900年以降に発生した自然災害を収録したデータベースである。データを収集する対象となるのは、次の4つのいずれかに該当する自然災害だ。
1. 死者が10人以上
2. 被災者が100人以上
3. 非常事態宣言の発令
4. 国際救援の要請
また自然災害は、以下の6種類に分類される。
・水理学的災害(洪水、地すべりなど)
・気象災害(嵐、極端な温度、霧など)
・気候学的災害(干ばつ、山火事など)
・地球物理学的災害(地震、火山噴火など)
・生物学的災害(感染症、害虫など)」
・地球外からの災害(隕石、宇宙天気など)
※上記のうち、水理学的災害、気象災害、気候学的災害を総称して「気候災害」と呼ぶ。
EM-DATでは、災害ごとに、物理的な特徴、人的・経済的な影響に関する数値、状況を記録したレポートを合わせてデータ化している。
グハ=サピール教授は、EM-DATの特徴をこう話す。
「災害に関する似たようなデータベースは他にもありますが、それらとEM-DATの決定的な違いがあります。EM-DATはすべてがシステム化され、全データが標準化されていることです。
標準化されることで、地域ごとの災害の影響度や経時的な変化の傾向が分かるのです」(グハ=サピール教授)

EM-DATには、現時点で過去122年分のデータを蓄積。データの正確さとカバー範囲の改善を続けている。
1980年代以降はデータの信頼性も高く、そこからはグローバルや地域の政策に生かすべき重要な情報が読み取れると話す。
「異常気候とその影響に関連する議論には、2つの重要なポイントがあります。
1つは、災害全体に占める"気候災害の割合の急増"です。直近の8年間は、全災害の約90%が気候災害となっています。
また、異常現象は多くの損失や被害をもたらしますが、専門機関による損害の見積もりは金銭的価値を持つものだけが対象で、人間が亡くなったり、障害が残ったりする損失は含まれていません。この見落としに注意する必要があります。
もう1つは、以前と比べて"各災害の深刻さが明らかに増している"ことです。1つの自然災害の被害規模が大きくなり、より多くの人々に影響を与えているのです。
気候災害は、直接的な被害だけではなく、例えば一家の稼ぎ手の死亡による生計の喪失、病気のまん延などももたらし、貧困化の要因にもなり得ます。
これら一連の変化は、明らかに気候変動、すなわち地球温暖化の結果の一部であり、考慮すべきです」(グハ=サピール教授)

Shutterstock / Piyaset
そもそもなぜ、グハ=サピール教授はこのような大規模な災害データベースを開発しようと考えたのか。
そのきっかけになったのが、1980年代半ばにアフリカのチャドで起きた大干ばつだ。彼女は、1984年にCRED(災害疫学研究センター)で疫学者および公衆衛生専門家としての仕事をスタート。その後チャドの被災地を訪れて、飢饉状況を徹底的に調査した。
「当時の上司に急いで犠牲者数などを報告すると、『犠牲者の数だけでは、政策をつくる動きにはつながらない』と指摘されました。
データは、例えば地域全体の人口や現場の状況など、他要素と組み合わせてはじめて意味を持つと言われたのです。
このアドバイスを受けてはっとしました。災害の人的影響を数量化するには精緻なデータの蓄積が必要で、データが標準化されて正しく提供されない限り、有用な情報にはならないと悟りました。
既に各国でさまざまな災害データが収集されていましたから、異なる情報源を検証する独立した中央集約的なシステムデータベースを構築することが、災害の救援と軽減のための有益な情報支援システムとして役立つと考えたのです」(グハ=サピール教授)

そうして作り上げたEM-DATだが、すぐに周囲や各国から受け入れられたわけではなかった。
「災害分野の著名な研究者たちからは、世界中から統一した形でのデータ収集などできるはずがないと否定されました。
また、災害対応のボランティアの人たちからも、人命救助を最優先とすべき場で、科学は二の次だと非難されたこともあります。
また90年代当時は、公的機関から私たちのデータに疑問を呈する干渉がしばしばありました。例えば災害についての死者数を発表すると、彼らは数字が大きすぎると主張したり、別の場合には小さすぎると主張したりしたのです」(グハ=サピール教授)
こうした状況にもめげずに、グハ=サピール教授たちのチームは独立した情報源からデータを収集。裏付けを取り続けた。
現地に足を運び、対話を続けてきた。
本人提供
その結果、徐々にEM-DATは世界で最もバランスの取れた信頼できるデータベースとの評価を高めていく。
次第に、国連や各国はEM-DATのデータを災害管理における政策開発に活用するようになり、国連の気候変動枠組み条約締約国会議(COP)や他のハイレベルな気候会議の状況報告では、EM-DATの分析結果が審議に使われるようになった。
「90年代半ばまでには、国連のさまざまな機関から信頼を得ました。加えて被災国や災害の影響を受けやすい国々の政府との関係も、非常に良好になっていったのです。
多くの政府が、正確な科学的データは、災害に対する政策を考える際の貴重な資料になると理解するようになりました」(グハ=サピール教授)
また近年は、IPCC(気候変動政府間パネル)の特別報告書や世界気象機関でも使用され、異常気象災害の分析にも用いられている。
EM-DATは、開発当初から信頼性のある疫学的原則と強力なデータベース管理の基盤があり、同じ定義を用いて全世界を網羅している。そのため、地域間の比較も容易になり、気候関連の災害により高いリスクに直面している場所や傾向が明らかになった。
「例えば、カンボジア、ベトナム、モザンビーク、バングラデシュなどの災害の影響を受けやすい国々では、市民団体がEM-DATデータを分析し、リスクの高い地域を特定することができるようになりました。
EM-DATは、災害リスク低減のために政府を動かし、支援を促す推進力となっています」(グハ=サピール教授)

グハ=サピール教授は本来、疫学の研究者だ。
研究を進める中で、従来の疫学モデルがウイルスなどの病気の拡散を説明できるだけでなく、地域内での自然災害への対応にも応用できるのではないかと考えるようになったと明かす。
「残念ながら、異常気象の人間への影響を理解するための疫学データはまだ質、量ともに不十分です。
洪水やサイクロン後の急激な環境変化により、飲料水の汚染や蚊やネズミなどの疾病媒介動物の増加、大規模な人の移動などが起こり、マラリアやコレラなどさまざまな病気が発生します。
EM-DATはこの数十年間で驚異的な進歩を遂げてきましたが、今、各組織内でデータが分散管理される問題を乗り越え、多様な学問領域のデータを統合するために協力することが急務です。
ほぼ避けられない気候災害の増加に備えるために、遠隔探査データや現地のデータ、周囲の情報を活用した良いモニタリングシステムが必要です」(グハ=サピール教授)
今回のブループラネット賞受賞は、災害データを次のレベルまで高める絶好の機会であり、自分の人生にとっても重要な節目になると振り返るグハ=サピール教授。
最後に日本の読者に向けて、貴重なアドバイスを語ってくれた。
「日本で異常気象に対処するにあたり、3つの大きな問題があります。
熱波、高齢化、そして一時的な大気汚染です。日本は大気汚染対策で成功を収めてきましたが、自動車の排出ガスや産業排出物は依然として一部の人々に問題を引き起こす可能性があります。
とくに大気汚染と熱波が重なると、その悪影響を大幅に増幅させることがあります。さらに、高齢者の多くが影響を受けやすいことを考慮すると、近い将来避けられない気候災害の影響が悪化することを懸念しています。
そんな中で、特にこれからの時代を担う日本の若者には、"もっと世界に出て、各国の出来事や他の文化を持つ人々、特に貧しい国の人々が異常気象に向き合う様子を自分の目で見てください"と伝えたいです。
彼らからは世界にとって良い教訓を得ることができるでしょうし、最も重要なことは、自分の"快適圏"を離れ、客観的なエビデンスに基づいた行動を取るような視点を育むことです」(グハ=サピール教授)
*グハ=サピール教授を含む、「ブループラネット賞」2023年受賞者による記念講演会が2023年10月5日(木)に東京大学で、10月7日(土)に京都大学で開催される。プログラムの詳細と参加の申し込みは、2023年8月1日より旭硝子財団のホームページで公開。
***
Business Insider Japan掲載記事
ブループラネット賞について詳しくはこちら


