af Magazine
〜旭硝子財団 地球環境マガジン〜
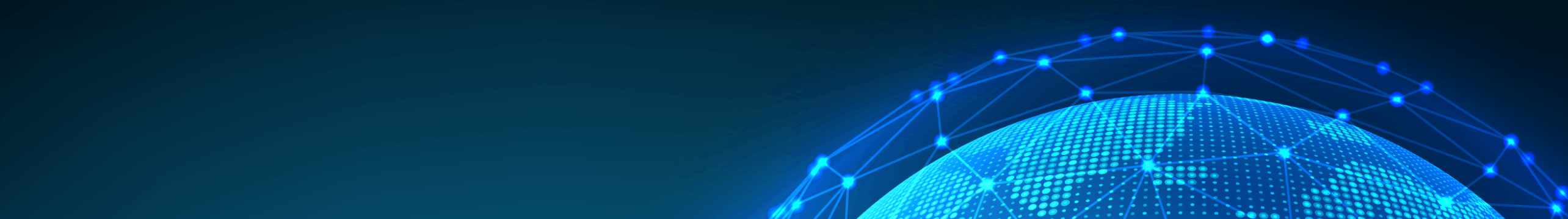

捨てたゴミが、100年海に漂うとしたら──? マイクロプラスチック問題の真実

深刻化する、マイクロプラスチックによる海洋汚染問題。
この分野の研究を続けるのが、マイクロプラスチック研究の第一人者とも言われるリチャード・トンプソン教授、 プラスチックの人体や生物への影響を研究するタマラ・ギャロウェイ教授、そして海洋生物や生態系への汚染を研究するペネロープ・リンデキュー教授だ。
「ひとたび海に流れ込んだマイクロプラスチックは、100年以上も残る可能性がある」という衝撃の事実もある中で、今何を思うのか。3名にオンラインでインタビューを行った。

本人提供
マイクロプラスチックとは、5ミリメートル以下の小さなプラスチックを指す。
ゴミとして捨てられたビニール袋やペットボトルなどのプラスチック製品が、やがて海に流れ込み、砕かれたり分解されたりしてマイクロプラスチックになる。
あるいは化粧品や洗顔料などに含まれている微細なプラスチック(マイクロプラスチックビーズ)は、そのまま下水を通じて海へと流されていく。

今ほど環境問題が意識されていなかった20世紀には、ビーチにプラスチックのゴミが散乱していても、気に留める人はそれほど多くなかった。
そんな中でも「こんな状態を放っておいてはいけない。特にプラスチックの破片、つまりマイクロプラスチックは大きな問題になるのではないか」と危機意識を持ったのがトンプソン教授だ。

本人提供
自分なりにマイクロプラスチックに関連するデータを集めた教授は、2004年に、世界初となるマイクロプラスチックに関する論文を筆頭著者として発表した。
「論文が公開される直前にキャンプに出かけたのですが、戻ってきてびっくりしました。メールボックスにあふれるほどメールが来ていて、電話もひっきりなしにかかってきたのです」(トンプソン教授)
世界中がマイクロプラスチックの問題に気づいたのだ。
その後トンプソン教授が問題提起してからの約20年間で、海洋のマイクロプラスチック問題に対する認知は世界中で高まった。
しかしこの間にもプラスチックは廃棄され続けていて、2019年のデータでは年間3億5800万トンのプラスチックが発生し、そのうち河川や海などへの流出は610万トンにものぼるという。
依然として膨大な量のマイクロプラスチックが海に流れ込み続けているのだ。

近年、マイクロプラスチックは海洋生物だけではなく、巡り巡って人の体内に取り込まれ、人体に悪影響を及ぼすことも懸念されている。
タマラ・ギャロウェイ教授は次のように語る。
「マイクロプラスチックが血液中を流れている可能性も指摘されていますが、体内のプラスチックを検出するのは極めて困難なため、実態はまだよく分かっていません」(ギャロウェイ教授)

本人提供
仮に、マイクロプラスチックが気づかぬうちに体内に取り込まれているとしよう。そのとき、どのような健康問題が起こるのだろうか。
「ごく小さな粒子が消化管から吸収され、毛細血管を通じて全身に運ばれる可能性があります。基本的にプラスチックは体内で分解されないので、どこかに蓄積すれば炎症を起こすことも考えられます。
あるいはプラスチックの添加物が撹乱要因となり、ホルモン伝達に異常を引き起こすリスクもゼロではありません」(ギャロウェイ教授)
実際に動物を使って行われた実験では、体内に取り込まれたマイクロプラスチックは全身に拡散。基本的に排泄されるものの、特定の組織や臓器への蓄積も見られた。
人体に対しても同様に何らかの悪影響を及ぼすと想定すれば、既に人類は取り返しのつかない危機的状況に陥っている可能性も否定できない。
「環境中、具体的には海洋中に、現時点で一体どれだけのマイクロプラスチックがあるのか、その絶対量は誰にも分かりません。
ただ、はっきりしているのは、早急に何らかの対策を講じなければ、マイクロプラスチックの影響は高まる一方だということです」(トンプソン教授)
かつて日本では、水俣湾の海水中のメチル水銀が原因で水俣病が発生した。
メチル水銀については食物連鎖のリスクが明らかになっている。メチル水銀を取り込んだプランクトンを小さな魚が食べ、さらにその小さな魚を大きな魚が食べる。結果として、大きな魚にはメチル水銀が濃縮され、それを人が食べて健康被害が起きたのだ。
「今のところ、マイクロプラスチックは、プランクトンなど食物連鎖の底辺にいるような小さな生物により高いリスクをもたらすようですが、食物連鎖におけるプラスチックの生物濃縮についてはほとんど証拠がありません。
今後どのように推移するかは注視する必要があります」(リンデキュー教授)

本人提供
プラスチックは単に人類に害をもたらすだけなのか。この問いに対して「それは違う」とトンプソン教授は答える。
「プラスチックは、便利で使いやすく、手頃な価格で多くの社会的利益を提供しています。プラスチック自体は素晴らしい資源と考えるべきです」(トンプソン教授)

問題は、プラスチックを使った「その後」だ。この問題の根源は、ほとんどの製品が一度しか使用されず、都合よく使った直後に廃棄されるように設計されていることだ。
この問題の本質を、ギャロウェイ教授は次のように指摘する。
「ほんの一時しか使わないものでも、海に捨てられた後は100年以上も海の中に残り続けるのです。
プラスチック製のパッケージを採用する人は、可能な限り低コストの製造法だと考えてきたと思いますが、廃棄されたプラスチックを処理するためのコストなどは、あまり頭になかったのではないでしょうか」(ギャロウェイ教授)
使用後までを考えずに製品化され問題となった典型例が、洗浄効果を高めたり、角質を除去したりする効果があるとされ洗顔料などに使用されたマイクロビーズだ。
洗顔の際に使われたマイクロビーズは、そのまま下水を通じて海へ流れ込む。いったん海に入ってしまうと回収はほぼ不可能で、海中に存在し続ける。
そのリスクをギャロウェイ教授、リンデキュー教授、トンプソン教授らが指摘し続けた結果、今ではEU諸国、アメリカ、韓国などでは政府によって使用が禁止されている国もある。
しかし、すでに海中に漂うマイクロビーズが今後、どのような影響をもたらすかは分かっていない。
だからこそギャロウェイ教授はこう訴える。
「何らかの形でプラスチックを利用している企業のみなさんには、ぜひ一度、プラスチック容器がゴミとして、大量に捨てられている海岸を見に行っていただきたい。
その状況を目の当たりにしても、現状のモノづくりに何の問題もないと考えられますか?と問いかけたいです」(ギャロウェイ教授)

「この半世紀ほどの間で世界の人口は急増し、プラスチックの使用も同様に増えています。
次の世代の人たちにとっての地球環境を考えると、現時点では想定されていない問題が発覚し、しかも急速に進行するおそれがあります。
そのような未来を防ぐために、残された時間は少ないのです」(トンプソン教授)
もとよりプラスチックには、原材料となる石油資源の枯渇問題もある。必要なのは、全体的なシステムの見直しである。
その際に求められるのは、資源としてのプラスチックの有用さを認識した上で、その価値を享受しながら廃棄物やごみとして蓄積しないようにする「システム思考アプローチ」だ。
「消費者としては、リフューズ(Refuse:断る、拒否する)を強く意識してほしい」とギャロウェイ教授は話す。
リフューズとは、ゴミの発生回避のこと。例えば製品を購入する際に過剰包装を断る、または本当に必要かを考え、不要な場合はそもそも購入しないなどの行動を取ることだ。
また必要だと判断した場合は、使用後はどうするのか、廃棄までを考える視点を持つことも大切だ。
リンデキュー教授もこう続ける。
「これまでは、リデュース(Reduce:減らす)、リユース(Reuse:繰り返し使う)、リサイクル(Recycle:再利用する)をまとめて『3R』と言われてきました。
これからは、リフューズ、リデュース、リユース、そしてリパーパス(Repurpose:アップサイクルする)の順で考えるべき。
リサイクルを最初の手段として考えていてはいけないのです」(リンデキュー教授)

世界中がプラスチック問題を認識した結果、国連環境総会の175カ国は、プラスチック汚染を減らすため法的拘束力があるプラスチック汚染に関する国際条約に向けて取り組むことで合意した。変化を起こす機運は高まりつつあるのだ。
地球の未来について、研究者たちはどのように考えているのだろうか。インタビューの最後に、10年後の理想の世界を聞いた。
「企業が問題を解決してくれていることを望みます。
例えばスーパーの店頭に並んでいる商品のパッケージが、廃棄時のことを十分に考慮したデザインになること。消費者は安心して商品を購入し、パッケージの行く末を心配する必要がありません。そこには大きなビジネスチャンスがあるでしょう」(トンプソン教授)
「私も未来についてはポジティブでいたいと思います。
プラスチックの製造、輸送、廃棄物処理、または管理を誤ると、温室効果ガスや汚染物質の発生につながり、結果として気候変動や生物多様性の喪失につながります。
しかし、必ずしもネガティブにとらえる必要はありません。自然環境にプラスチックやゴミが捨てられているところを見たい人などいません。
プラスチックは社会にとって大きな利益をもたらすもので、賢明にプラスチックを設計、利用、管理すれば、私たちは引き続きプラスチックを使用することができるのです。
解決策は自然の中にあるかもしれません。それを実現するためのイノベーションも起こるでしょう。その際にはあまり利益を追求しすぎないことも大切です」(リンデキュー教授)
「一人ひとりが他人任せにせず、自分の問題として向き合う。例えば自分たちが暮らす地区単位でリサイクルに取り組むのが当たり前になっていてほしい。そのためには製品設計はもとより、都市設計も考え直していく必要があるでしょう。
大きなことをしなくてもいいんです。ローカルなレベルでサステナブルな生活を一人ひとりが強く意識すれば、未来は変わるはずです」(ギャロウェイ教授)
***
*トンプソン教授、ギャロウェイ教授、リンデキュー教授を含む、「ブループラネット賞」2023年受賞者による記念講演会が2023年10月5日(木)に東京大学で、10月7日(土)に京都大学で開催される。プログラムの詳細と参加の申し込みは、2023年8月1日より旭硝子財団のホームページで公開。
Business Insider Japan掲載記事
ブループラネット賞について詳しくはこちら

