af Magazine
〜旭硝子財団 地球環境マガジン〜
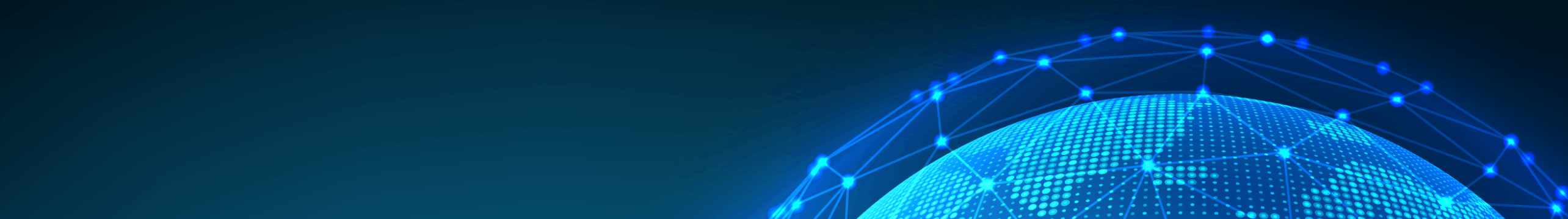

人口減少社会における、ヒトと野生動物の共生とは? ニホンザルのマネジメントから考える
- 助成期間:2020年5月〜2023年3月
- 採択テーマ:ニホンザルの個体群管理の適正化に資する低コスト・モニタリング技術「ボイストラップ法」の開発
日本の農村地域で深刻さを増している獣害問題。2023年はクマ類による人身被害が多発し、大きく報道もされました。クマ類だけでなく、この十数年対策が急がれてきたのが、農業被害をもたらすニホンジカ、イノシシ、ニホンザルの管理の問題です。哺乳類生態学、とくにニホンザルを専門とする山形大学学術研究院の江成広斗教授は、ニホンザルの生態を探ると同時に、その管理方法を社会実装するための研究を続けてきました。人口減少社会が到来した今、私たちと野生動物の間にどのような問題が起きているのか、そしてどう共生し得るのか。江成教授に聞きました。
「保護」から「コントロール」へ。人間社会の移り変わりとともに、サルの管理方針も変化してきた

近年、日本の農村地域では野生動物が大きな問題となっています。とくに、ニホンジカ、イノシシ、そしてニホンザルによる農業被害は後をたたず、農村部の住民はその対策に追われています。学生時代からニホンザルの生態を調査してきた山形大学の江成広斗教授は、ニホンザルの管理方法についての研究にも力を入れてきました。江成教授は、「現在私たちが直面する野生動物の問題は、人口減少社会が到来し、農村集落の体力が自然の力に対して相対的に弱まったことによって深刻化している」と言います。
「歴史を振り返れば、私たち人間社会の変化とともに野生動物の管理方法も大きく変化してきました。戦後は、大規模な開発や乱獲の影響を受け、野生生物の分布の減少が問題に。ニホンザルも絶滅寸前まで個体数が減少し、保護政策が取られました。しかしその後、サルの個体数が回復した一方で農村の人口は減少し、サルが集落に出没し農業被害をもたらすようになりました。そして、約10年前、捕獲による個体数のコントロールへと方針が転換されたのです」
個体数のコントロール自体は必要としながらも、江成教授は同時に問題点も指摘します。
「捕獲の方法や計画性の不足に問題があると考えています。この10年、日本の野生動物の捕獲技術は目覚ましい進歩を遂げてきました。例えばニホンザルの場合、群れで行動する彼らを、丸ごと捕獲する技術が確立してきました。もちろん群れごとの捕獲が有効な場合もあります。しかし、計画性なく群れごと捕獲した結果、広域的にニホンザルが姿を消した地域の事例も出てきています」
環境省は、ニホンザルについて、群れの加害レベルに合わせた対策を呼びかけています。「群れの全頭捕獲」は加害レベル4〜5で検討される施策です(※)。しかし、この加害レベルの判定は「通年、週に2、3回近くどこかの集落で見かける」「甚大な被害を受けている集落がある」など、主観的判断項目も多く含まれます。江成教授によれば、被害を受けている住民が判断すると、どうしても感情に左右され、加害レベルを高く見積もってしまうことも多いのだそうです。
「反対に、保護しなければという価値観が強く働き、捕獲が妥当な加害性のある群れを全く捕獲しない地域もあります。計画的な管理を行うために、客観的情報で加害性を判断できるようにすることが必要だとずっと考えていました。そのために取り組んだのが、今回助成を受けた"ボイストラップ法"による加害性評価の研究でした」(江成教授)
※加害レベルとは、群れのもつ人や集落への加害性を指し、0~5の6段階で評価。環境省が定める「特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(ニホンザル編)」の2024年改訂版から加害レベル4~5が群れ捕獲対象となることが明記される予定
労力をかけず、広範囲で検知できるボイストラップ法。「高い確度で群れの加害性を評価できた」

江成教授は、すでにニホンジカの鳴き声を利用したボイストラップ法を開発しており、その手法をニホンザルに応用できるはずだと考えていました。
「群れで行動するニホンザルは、2分に1回程度の高い頻度で"コンタクトコール(通称、coo call・クーコール)"を鳴き交わし、お互いの位置を確認して集団を維持します。こうした高頻度で発せられる鳴き声を検出し、分析すれば、客観的に加害性を判断する情報になり得るのではないかと思っていました」
江成教授は、白神山地と朝日山地に高性能録音機を設置し、2020年〜2021年にかけてデータを収集、鳴き声の解析を行いました。その結果、鳴き声の連続性と頻度から、集落内における群れの滞在時間と襲来回数を比較的容易に分析できることがわかり、その2つの情報を用いて、高い確度で加害性を分類できることも判明しました。
「この結果だけでも、ボイストラップ法をサル被害が問題になっている現場で活用できる可能性は充分にあります。ただ、今回の結果はじつは、収集した鳴き声情報のごく一部を用いたものに過ぎません。データからは、コンタクトコールのほかに、音響的特性の異なるさまざまな種類の鳴き声の抽出に成功しています。それらの鳴き声の言語的な意味を評価し、分析することができれば、加害レベルの判別精度をもっと高められるはずです。今後の課題として、現在も研究を進めています」(江成教授)
普通種の哺乳類がいなくなるインパクトはどれくらい? 根拠ある生物多様性保全のために

もうひとつ、江成教授が基軸としている研究テーマがあります。それは、「害獣」と呼ばれがちな普通種の哺乳類が生態系に何をもたらしているのか、彼らがいなくなると森林にどんなインパクトがあるのかを調査することです。生物多様性保全というキーワードを聞くと、希少種の保護をイメージしがちですが、江成教授は、個体数の多い普通種がじつは森林生態系の機能を支える屋台骨になっていると語ります。
例えば、ニホンザル。ニホンザルと、サルが排泄する糞に集まるコガネムシは、互いに役割を果たすことで種子散布の機能を高めることがわかってきました。サルは果実を食べることで種子を運搬し、排泄された糞はその中に混じる種子ごとコガネムシによって土中に埋められます。土中の種子は、大雨や台風などによって森が傷ついた際に、その再生を担う重要な役割を持っています。
「ニホンザルのいない森では、コガネムシも減少し、森林の再生能力が低下することがわかりました。そのような森は、気象災害に対して非常に脆弱になっている可能性があります」(江成教授)
江成教授は、ニホンザルだけでなく、イノシシ、クマ、シカについても調査を進めており、徐々にそうした普通種の果たす役割が見えてきたと言います。生態系の機能を円滑に維持していくために必要な個体数と、人間が安全・安心に生活を営んでいくために捕獲しなければならない個体数。今後は、両方の視点を考慮した野生動物の管理計画を立てていくことが必要だと江成教授は言葉に力を込めます。
「生物多様性保全に対する理解は拡大していると感じますが、現場で実際に生物多様性の保全計画を考えようとする時、活かせる研究の蓄積はまだまだ不足していると言わざるを得ません。多様な種がどのように関わり合って生態系を支えているのか。生物多様性保全のための活動を止めないよう、我々研究者が調べ、根拠をきっちり積み上げていかねばなりません」
動物とヒトの共存とは何か。人間社会のあり方を問い、地域住民とゴールを考えることが必要

江成教授は、野生動物に関して社会が必要とするデータを、その成果に基づく研究成果を社会問題の解決のために展開(社会実装)するところまでが自分の研究だと言います。その背景には、調査フィールドで出会った住民たちの切実な声がありました。
「ニホンザルの調査に来たと伝えると、住民の方にはよく"観察していないで追い払ってくれよ"と言われます。研究者であればこそ、そんな住民の声にちゃんと応えるべきだと思うのです。しかし今、こんなにも地域で野生動物が引き起こす問題が深刻化しているにも関わらず、日本で野生動物のマネジメントを研究する人は非常に少ないのが現実です。野生動物の生態を探って終わりではなく、地域に役立つアウトプットに繋げることにこそ価値があると考えています」(江成教授)
江成教授が大事にしている、地域への眼差し。地域に役立つ研究をするためには、野生動物の生態を探ると同時に、人間社会のあり方について考えることも必要になります。人間社会がこれから歩む道によっても、野生動物とヒトの関わり方は変化するからです。
「獣害を語る時、指標として農業被害額が用いられがちですが、それは問題の一側面。何が本当の被害で、問題の解決とは何か。それは、よそ者から与えられるものではなく、地域の方々にしかわからないことです。地域住民と一緒に考えることなしに、野生動物とどう関わるか、その問いへの答えは出ないと思っています」(江成教授)
江成教授が働きかけた結果、山形大学は、10年前から、大学の重点研究課題に人口減少社会における野生動物管理の問題を採択。学外の研究機関・行政・民間企業とも連携し、新しい管理のあり方を探ってきました。その一環として、江成教授らは産官学の多様な関係者が一堂に会し、野生動物管理に関わる情報共有を進めるプラットフォームとして「東北野生動物管理研究交流会」を企画。多様な関係者が一堂に会する機会を作ってきました。新型コロナウイルスの流行による中断まで計6回開催し、毎回約200名の参加があったそうです。
さらに、2024年4月、山形大学は、野生動物管理の推進を一つの軸とした農山村リジェネレーション共創研究センターを設立。地域づくりを主眼に置き、江成教授が所属する農学部だけでなく、社会学的アプローチ、感染症などの医学的アプローチなど、学際的な視点から野生動物のマネジメントを考えていく研究拠点となるのだそうです。
「ヨーロッパや東アジアでも、人の生活圏内における野生動物の問題が顕在化していて、よく問い合わせがあります。こうした国々でも急速な人口減少社会の到来は目前に迫っており、人と野生動物との関わりが新たな局面を迎えているのでしょう。日本の東北地方はこうした野生動物問題の研究において、世界の最先端と言える場所です。だからこそ、私はこの現場に身を置いて研究し、その成果を世界に発信していきたいと考えています」(江成教授)
江成教授は、獣害に直面する地域住民に対して、「解決を諦めないでほしい。必ず何かできることはあります」とメッセージを送る一方で、野生動物とは縁遠い都市に生活する人たちにも、この問題について心に留めておいてほしいことがあると語ります。
「野生動物問題の対処において、しばしば個々人の価値観が衝突します。例えば2023年には、人的被害の相次いだクマの駆除について抗議の電話が殺到し、行政機能をストップさせたことが話題になりました。命を大切にしたい、そうした価値観はもちろん重要です。ただ、前提として、この問題には『唯一の正解』は存在しないだろうということを理解してほしいと思います。野生動物の管理について前向きに議論を進めるために重要なのは、相互の批判ではなく多様な価値観の理解であり、都市と農村で協力できるポイントを探していくことが必要です」
Profile
江成 広斗(えなり ひろと)
山形大学学術研究院 教授
学生時代から、世界有数の豪雪地・白神山地を対象に、ニホンザルの越冬生態を調査。2013年より山形大学農学部准教授となり、野生動物管理や森林生態系における野生動物の役割にも焦点をあて研究を行う。2021年4月より山形大学学術研究院(農学部配置)教授、岩手大学大学院連合農学研究科教授。環境省・特定鳥獣保護管理検討会(ニホンザル保護及び管理に関する検討会)検討委員や日本哺乳類学会哺乳類保護管理専門委員会の委員なども務めている。共著に『哺乳類学』(東京大学出版会、2022年)。

