af Magazine
〜旭硝子財団 地球環境マガジン〜
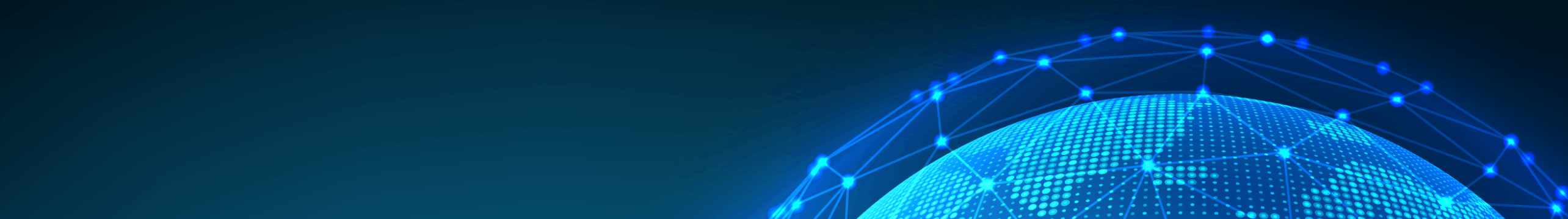

世界のGDP超える「年間125兆ドル」──生態経済学の第一人者に聞く「生態系」の価値

"現代の経済システムのなかで、これまで何百万年もの長い時間をかけて培われてきた地球の生態系は脅かされつつある──"
このことにいち早く着目したのは、「生態経済学」という新しい学術分野を創出し、持続可能な社会の実現に向けた政策提言を行っている、ロバート・コスタンザ教授だ。
教授が2014年に発表した研究成果によると、全世界における生態系サービス(生態系から社会が得られる恵み)の価値は、年間125兆ドル(2007年の米ドル価値換算)にものぼるという。
"成長重視"の現代社会で見過ごされてきた生態系サービスの価値に目を向け、ウェルビーイングな社会を実現するにはどうすればいいのか。独自の研究結果や長年の活動から導き出した解決策について、コスタンザ教授に聞いた。

私たちの生活は、食料や水、原材料の供給、気候の調整など、自然(生物多様性)から得られるさまざまな恵みによって支えられている。このような人類に恩恵をもたらす自然界の資源や生態系の機能は、「生態系サービス」と呼ばれ、次の4つに分類される。
この生態系サービスと経済学を組み合わせたのが、2024年のブループラネット賞を受賞した一人で、生態経済学者のロバート・コスタンザ教授だ。
コスタンザ教授は、生態経済学に着目した理由をこう振り返る。
「生態系サービスは、人間の福祉に直接的、間接的の両面で貢献していて、地球全体の経済価値の一部を占めています。
しかし私が研究を始めた頃は、いわゆる経済効果のような形で定量化されておらず、政策決定においても軽視されがちでした。
このままの状態が続けば、人類の持続可能性を損なうことになりかねない。
経済学や生態学、心理学など、既存の学術領域をばらばらに研究するだけでは不十分だと思いました。そこで、学術的な領域を横断したアプローチが必要だという考えに至ったのです」(コスタンザ教授)

コスタンザ教授は、CBD(生物多様性条約)が採択されるよりも早い1989年に、2014年にブループラネット賞を受賞したハーマン・デイリー教授とともにISEE(国際生態経済学会)を設立し、初代会長に就任。経済は社会と有限な生物圏に組み込まれていると考える、生態経済学の礎を築いた。
その後1997年に、イギリスの科学雑誌『Nature』に論文『世界の生態系サービスと自然資本の価値』を発表。
論文内で、全世界の生態系サービスの価値を初めて体系的に試算し、当時の米ドル換算で年間33兆ドル(2007年のドル換算で44兆ドル相当)もの貢献があると推算されることを明らかにした。
この金額は当時の世界のGDPを上回る価値で、それまで見過ごされ、過小評価されていた生態系サービスの価値を世界に知らしめることとなった。
2014年には、2011年の新しいデータを使い生態系サービスの価値を改めて試算。生態系サービスの推定価値は、年間125兆ドル(2007年の米ドル換算)となった。
その後2011年以降は、生態系サービスは一定の安定化が図られていると考えています。
2022年12月に開催された生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)では、『昆明・モントリオール2030年目標』の一つに、2030年までに陸と海の少なくとも30%を保全するという目標も採択されました。
また、中国など一部の国では湿地の保護などに取り組んでいます。このような動きも後押しとなり、特にここ最近、生態系を復活させようとする動きは加速しています」(コスタンザ教授)

Shutterstock / R.M. Nunes
生態系サービスを守るためには、国だけでなく企業、そして個人もアクションを起こさなくてはならない。
コスタンザ教授は、「いま必要なのは、成長中毒社会からの脱却」だと警鐘を鳴らす。
いわゆる"不経済な成長"への危惧で、その副作用の一つには、生態系サービスの損失も含まれる。「我々は、これまでの成長中毒を乗り越える必要がある」とコスタンザ教授。
そのためには、GDP(国内総生産)にこだわるのではなく、より広範囲でウェルビーイングな指標を目標としていくべきだと語る。
「GDPは国の豊かさの指標としても使われますが、社会のウェルビーイングを測定するために設計された指標ではありません。
GDPの代替指標であるGPI(Genuine Progress Indicator:真の進歩指標)やHPI(Happy Planet Index:地球幸福度指数)に移行する必要があるのではないでしょうか。
実際に、国連や世界銀行も新しい指標を考えています。優れた指標を探索し続け、GDP一択の使用を切り替えるために必要な、幅広いコンセンサスを得る必要があります」(コスタンザ教授)

Shutterstock / Song_about_summer
「GDPに代わる包括的な指標を採用することで、気候変動に対応しない政策や再生可能エネルギーへの移行を邪魔する政策などを変えることもできるはず」と教授は続ける。
「より良い社会へと変化させることこそ、生態経済学の根本的な目標です。
生態系サービスの価値、経済、社会のウェルビーイングへの貢献を認識し、何が必要であるかを理解すれば、現在の"成長中毒"を乗り越え、サステナブルで望ましい将来が望めます」(コスタンザ教授)
必要なのは、より広い意味での社会的幸福へのシフトだ。
「現代は物質主義が行き過ぎています。必要なだけ持つ。それで十分ではないですか。
一部の人が持ちすぎている状況を許容するべきではありませんし、持ちすぎているのであれば、再分配して公平な形で分け与えるべきです。
"もっと欲しい"という個人の欲は捨てなくてはいけません。地球には限界があるわけですから」(コスタンザ教授)
人・環境が調和した社会には、自然資本や生態系サービスへの理解が欠かせない。
そのためにも、生態経済学は重要な役割を担っている。今回のブループラネット賞の受賞も、その重要性が認められた証しだ。
「(過去の受賞者である)ハーマン・デイリー教授を始めとして、これまでの受賞者には各分野の優れた専門家が並んでいて、その仲間に加われたことは非常に嬉しく思っています。
この受賞により生態経済学、そして生態系サービスがさらに注目を集めて、よりよい社会を作る一助になれば喜ばしいことです」(コスタンザ教授)

コスタンザ教授は、今後さらに挑戦したい研究があると語る。
それは、成長中毒の延長線ではない、サステナブルでウェルビーイングな未来、いわば"代替的な未来"を人々が受け入れるかどうかの調査だ。
「オーストラリアで、4つの未来シナリオを示して意見を問う調査を実施しました。これをグローバルに広げて、一般市民のフィードバックを得たいと考えています。
現在の延長線とは異なる"代替的な未来"があり得ることを理解していない人も多い。その可能性を提示することで、人々の意識を探ってみたいと思います。
それをきっかけに議論を促し、大勢の人々が生態系サービスの保全と、幸福を重視する社会づくりに積極的に関わってくれることを望んでいます」(コスタンザ教授)
1992年、CBD(生物多様性条約)の採択、2005年、MA(ミレニアム生態系評価)の発表、そして、2021年、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)の発足など、生態系サービスをみんなの資源(共有資源)として捉え、全員の利益のために管理すべきだという動きが盛んになっている。
しかし、まだまだ取り組むべき課題も多い。コスタンザ教授の話は、成長中毒に偏った先にある未来に警鐘を鳴らし、今ならばまだ選ぶことができる持続可能な未来の実現に向けて、示唆に富むものだ。そしてその未来は、国や企業はもちろん、一人ひとりの判断や行動に委ねられている。
***
*「ブループラネット賞」2024年受賞者による記念講演会が2024年10月24日(木)に東京大学で、10月26日(土)に京都大学で開催される。プログラムの詳細と参加の申し込みは、2024年8月ごろ旭硝子財団のホームページで公開。
***
Business Insider Japan掲載記事
ブループラネット賞について詳しくはこちら

