af Magazine
〜旭硝子財団 地球環境マガジン〜
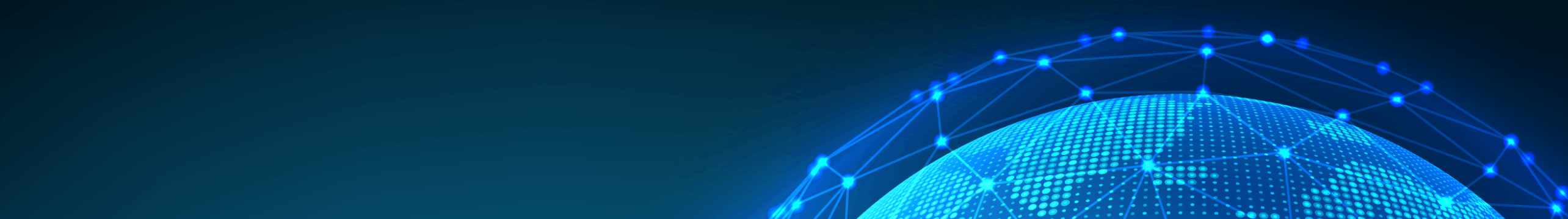

近い将来、地球上から100万種の生物がいなくなる? 「生物多様性」が必要な理由

"現状を放置すれば、地球上の生物多様性が大きく損なわれ、絶滅した生物種は二度と蘇らない──".
そう警鐘を鳴らすのは、生物多様性の動向を科学的に評価する政府間組織、IPBES(イプベス)事務局長のアン・ラリゴーデリー博士だ。
IPBESは、地球の環境問題の解決に向けて優れた研究をした人・組織に贈られる国際賞「2024年(第33回)ブループラネット賞」(主催・旭硝子財団)を受賞することが2024年6月に発表された。これまでの取り組みが評価された形だ。
今回Business Insider Japanでは、生物多様性にまつわる現状やIPBESの取り組みについて、ラリゴーデリー博士にオンラインでインタビューを行った。

「現状を放置し続けると、地球上の全動植物の8分の1ほどにあたる約100万種が、数十年以内に絶滅する可能性があります。
私たち人間は、生活に必要な食料や水、清浄な空気などを、健全な自然生態系に頼って生きています。
それほど大切な自然であるにもかかわらず、自然からの恩恵の多くは過去50年間、減り続けているのです」(ラリゴーデリー博士)
博士がこう語るように、人類は、地球の歴史上かつてない速度と規模で自然や生態系を破壊している。
淡水の生態系でいえば、1970年に存在した面積の85%がすでに消滅するなど、地球の全表面の4分の3以上が人類の活動によって大きく変わってしまった。
そして生物多様性の損失は、当然、私たちが暮らす地球の生態系の機能にも大きなダメージを与えていて、私たちのウェルビーイング(幸福)に欠かせない自然からの恩恵にも深刻な影響を及ぼしているのだ。
例えば、農作物を育てるために欠かせない動物による授粉、疾患や感染症の予防、土壌や淡水の維持など......自然界の調整機能は生物多様性に依存しているが、それらの機能は人間の活動によって著しく損なわれている。
「その一方で、食料や繊維などの生産、木材を中心とする建設材の供給など物質面の依存度は高まっています。
偏った過剰な自然開発によって生物多様性を損ない、これまで享受してきた自然からの恩恵が得られなくなっているのです」(ラリゴーデリー博士)
生物多様性を保全・回復するためには、今すぐにでも私たちは価値観を変え、社会のあり方そのものを変えていかなければならないことは明らかだ。

地球の自然環境に対する人びとの関心は、まず気候危機に向けられた。
1988年にIPCC(気候変動に関する政府間パネル)が設立。1992年にリオ・デ・ジャネイロで国連環境開発会議(地球サミット)が開催され、国連気候変動枠組条約 (UNFCCC)と生物多様性条約 (CBD)、国連砂漠化対処条約 (UNCCD)のいわゆる「リオ3条約」が採択された。
生物多様性はというと、長い間気候変動ほど注目されず、2005年になってようやくミレニアム生態系評価の報告書が発表された。
「報告書は現状に危機感を覚えた科学者たちが自発的に参加して作成したもので、生物多様性の問題を扱った世界初の環境報告書です。
国際社会にとっての生物多様性の重要さや、人間に対する影響などが明らかにされ、大きなインパクトを与えました。
ただし当時、このような報告書を継続的に作成する仕組みはなく、政府の関与もありませんでした」(ラリゴーデリー博士)
その後、"気候変動を評価しているIPCCのように、生物多様性についても継続的に評価できる仕組みを立ち上げる必要がある"と国際的な協議が始まり、2012年に90カ国以上の政府がIPBES設立を決定、ドイツのボンに事務局が置かれた。

IPBESは、まず2016年に『花粉媒介者、花粉媒介及び食料生産に関する評価報告書』を発表。
報告書では、ミツバチや蝶などの花粉媒介動物が世界中で減少している状況を明らかにし、食料の安全保障に対して深刻な脅威となっているとの警告が出された。
「さらに(社会に)強いインパクトをもたらしたのが、2019年に発表した『生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書』です。
IPBESが3年間ほどの年月をかけてプロジェクトを進め、世界で総勢500人の科学者が参加、1万5千件以上の科学論文や資料を包括的にレビューした結果をまとめました。
この中での主要な発見の一つとして、100万種もの動物や植物が絶滅の危機に瀕している実態が明らかになったのです」(ラリゴーデリー博士)
同報告書を受け、第15回の国連生物多様性条約締約国会議(COP15)では、2030年までに"生物多様性の損失を止め、反転させ、回復軌道に乗せるための緊急な行動をとる"といったミッションが定められた。

その後、IPBESは2022年に『自然の多様な価値と価値評価の方法論に関する評価報告書』を発表。
この報告書で強調されたのは、人びとが生物多様性を過小評価しがちな現状だ。自然から得られる短期的な経済価値や市場関連の価値ばかりを優先し、自然が人びとにもたらす非市場的・長期的な貢献を見落としているというメッセージを発信した。
さらに報告書では、人と自然の関わりについても言及されている。ラリゴーデリー博士いわく、人と自然の関わり方には、大きく次の4つがあるという。
その上で博士は、今の世の中は"Living from Nature"に偏り過ぎている、と続ける。
「かつて日本を訪れたとき、大木のまわりに太い縄を巻き、木そのものの存在に特別な価値を認めている姿に感銘を受けました。
それは国の天然記念物でしたが、これこそ人が自然の中に市場価値とは異なる価値を見出している象徴的な事例であり、自然の非物質的な価値を認める"Living as Nature"そのものだと感じました。
そういった価値観をもっと大切にしていくべきだと思っています」(ラリゴーデリー博士)

さらに同報告書は、科学や政策のコミュニティのみならず、世界の著名人にも強烈なインパクトを与えた。
「報告書を読んだ後、ローマ教皇、政治家のアル・ゴアやヒラリー・クリントン、レオナルド・ディカプリオ、南アフリカ出身のコメディアンであるトレバー・ノア、環境活動家のグレタ・トゥーンベリなど、世界的な著名人がSNSやメディアを通じて生物多様性の重要性を訴えました。
これまで著名人や若い人の関心は主に気候変動に向けられていましたが、IPBESは生物多様性の問題を、気候変動と同様の緊急性と優先度に引き上げるのに貢献したと考えています」(ラリゴーデリー博士)
設立して10年が経過した今、IPBESは科学政策プラットフォームとして確固とした存在となり、政策決定のための豊富なエビデンスと選択肢を提供している。
現在は、生物多様性に関する指針を求める企業からの要望も多く、IPBESは企業がどのように生物多様性をより良く保護・回復・活用できるのかについても積極的に調査・研究を行っている。

「IPBESは、2025年に『ビジネスと生物多様性』をテーマとする報告書を発表する予定です。
主な内容は、企業が生物多様性の管理と回復において果たす役割についてです。
世界経済フォーラム(WEF)が発表している『グローバルリスク報告書』でも、2020年以降毎年生物多様性が取り上げられていて、グローバル企業にとって重要な課題となっています」(ラリゴーデリー博士)
すでに、例えば自然破壊を助長する企業や、有害物質を自然に放出する企業への投資を控える金融機関の動きもある。
企業に求められるのは、自社のサプライチェーン全体を見通す問題認識とその改善だ。また、同じく都市も重要なプレイヤーであり、サンフランシスコ市では都市計画の中に生物多様性の視点を取り込んでいる。

G7の議長国を務めた日本に対して、ラリゴーデリー博士は「環境大臣会合の際、日本が侵略的外来種のトピックを取り上げたことで、多く注目を集めるきっかけになった」と評価する。
今回のブループラネット賞受賞について、そして今後の展望について、最後に次のように語った。
「(ブループラネット賞と聞いて)アメリカの天文学者で作家であるカール・セーガンの"地球は広大な宇宙というアリーナの、とても小さなステージだ"という言葉を思い出しました。
宇宙からみたらちっぽけで弱い地球を、私たちの手で守っていかなければなりません。
そして、IPBESの活動は、"かすかに青く光る点"である地球の隅々から集められたエビデンスや知識、専門家の知見に基づいて、新しい視点から自然界を見直す機会を提供しています。
IPBESに協力する研究者たちは、基本的に無償で時間と専門知識を提供してくれています。なぜなら、自分たちの研究が生物多様性の保全と回復に役立つと信じているからです。
今回の受賞は、彼らも喜んでくれるはず。今後も、さらなる活動の発展に励んでいきたいと思います」(ラリゴーデリー博士)
***
*「ブループラネット賞」2024年受賞者による記念講演会が2024年10月24日(木)に東京大学で、10月26日(土)に京都大学で開催される。プログラムの詳細と参加の申し込みは、2024年8月ごろ旭硝子財団のホームページで公開。
***
Business Insider Japan掲載記事
ブループラネット賞について詳しくはこちら

