af Magazine
〜旭硝子財団 地球環境マガジン〜
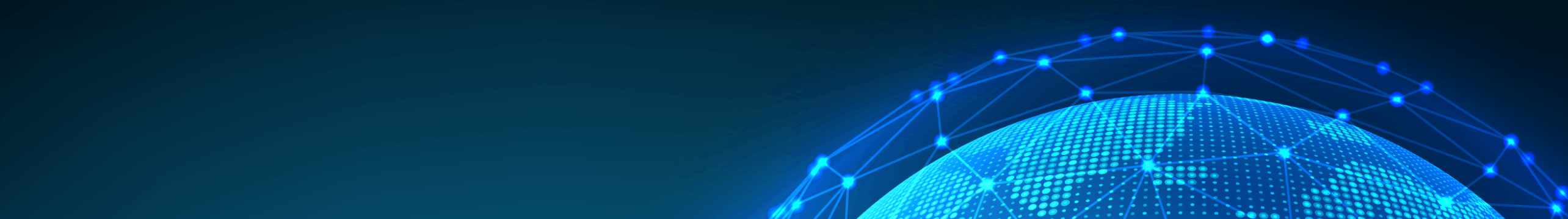

「生物多様性保全への対応は、大きなビジネスチャンス」専門家がそう語る理由

企業活動を行う上で、気候変動対策と並んで重要となっているのが「生物多様性」への配慮だ。
今、世界や日本ではどのような動きがあるのか。また、企業はどんな視点を持って生物多様性の保全に取り組むべきなのか──?
さまざまな企業に対して、サステナビリティの視点からコンサルティングを行っているレスポンスアビリティの足立直樹氏に、生物多様性に関する問題の現状や先進企業の取り組み、今後のビジネスチャンスについて話を聞いた。
企業が生物多様性に目を向け始めた
1992年、ブラジルのリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議(UNCED、地球サミット)。生物多様性条約は、この会議で気候変動枠組条約とともに署名が開始された。
同時にスタートした2つの条約は「双子の条約」と言われたものの、先んじて具体的な取り組みが進んだのは、二酸化炭素の排出量などを可視化しやすい気候変動への対応だった。

Shutterstock / bettapoggi
そして、生物多様性保全への取り組みは、ここ数年で急激に進んでいる。
その理由の一つに、2021年のTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)設立がある。TNFDは、民間企業や金融機関が、自然資本や生物多様性に関するリスクや機会を適切に評価し、開示するための枠組みの構築を目指す国際的な組織だ。
企業が事業のサステナビリティ情報を開示する場合、TNFDの基準に基づくのが一般的となっている。

Shutterstock / Fahroni
また、2022年12月の国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」のターゲット15では、企業が生物多様性への影響をモニタリングし、開示することなどが定められた。
こういった流れもあり、いよいよ生物多様性保全に本気で取り組まなくてはならないという機運が高まっているのだ。
生物多様性のいまを知る、3つのキーワード

ブループラネット賞WEBページより
生態学で博士号を取得した後、国立環境研究所での勤務を経て、現在は企業へのサステナビリティのコンサルティングを行う足立直樹氏は、生物多様性と企業活動を考える上での重要な流れを3つ挙げる。
1つ目は「依存」、2つ目は「ネイチャーポジティブ(自然再興)」、3つ目は「NbS(Nature-based Solutions:自然を活用した解決策)」だ。
「まず私たちは、日々の活動が自然・生物多様性に『依存』していることを理解しなくてはいけません。実際にWEF(世界経済フォーラム)は、生物多様性がもたらす経済価値を44兆ドルと試算しています。
2024年のブループラネット賞受賞が決まったIPBESは、この依存を"Living from Nature(自然によって生きる"と表現)しました。
また、ロバート・コスタンザ教授は、全世界の生態系サービスの価値(人間が生態系にいかに依存しているか)を初めて体系的に試算した功労者です」(足立氏)
自然・生物多様性への『依存』を十分理解した上で、自然破壊や生物多様性の喪失を食い止め、反転させ、回復させることが2つ目の『ネイチャーポジティブ』だ。
「日本で2023年3月に閣議決定した『生物多様性国家戦略2023-2030』でも、ネイチャーポジティブの達成が目標に掲げられています。
一方ネイチャーポジティブの実現にあたっては、経済活動や社会への影響を伴うと懸念する声もあります。
そこで注目されているのが3つ目の『NbS』。
例えばマングローブ林の保全をすることで洪水被害を軽減するなど、自然の力を活用して生態系と人々の両方に恩恵をもたらすやり方で、社会的な課題を解決していくのがNbSのアプローチです」(足立氏)

足立氏のもとには、日々さまざまな企業から生物多様性に関する相談が寄せられていると言う。その8割は、TNFDに関することだと話す。
「TNFDの基準をいち早く採用して情報を開示しようとする企業を、"TNFDアーリーアダプター"と呼びます。
2024年1月に世界320社のTNFDアーリーアダプターが発表されましたが、4分の1にあたる80社は日本企業で、賛同への動きは加速しています。
最近では、より本質的な理解を深め、ネイチャーポジティブなビジネスに踏み込みたいという相談も増えてきました。
特に、自然環境と自社事業の関係が密接な企業ほど、しっかりと考え、動き始めている印象です」(足立氏)
生物多様性に積極的に取り組んでいるセクターは、農業と密接な関係がある飲料・食品業界、材料に木材を使用する建設業界、水を大量に使用する化学業界、植物や微生物から新薬を開発する製薬業界、綿花や皮革を使うアパレル業界......そして、企業に投融資して間接的に生物多様性への影響がある金融業界など、多岐に渡るという。
例えばサントリーは、工場の水源エリアに広がる全国20カ所以上の森で水資源を守るために生物多様性の保全に取り組んだり、自然環境のバロメーターといわれる野鳥の保護を続けたりなど、精力的に生物多様性の再生を目指している。
住友林業グループは、木材資源を生産・確保するため、国内外で多くの森林を所有・管理する。リスクアセスメントの上で、生物多様性保全の観点から重要と判断された地域においては、法令遵守にとどまらず、事業活動の見直しや縮小を行い、生物多様性の回復に努めているという。
また三井住友信託銀行は、企業の生物多様性への取り組み状況の調査結果を参考にしつつ、財務面から分析・評価を加え、投資対象企業を決定する「生物多様性企業応援ファンド」を運用している。

もちろん、全ての企業が生物多様性の保全に積極的なわけではない。足立氏は、「本当の意義を理解している企業やビジネスパーソンは、まだまだ少ない」と指摘する。
その上で、例えば食品業界の企業で生物多様性についての認識不足やその保全への対応が遅れた場合のリスクとして以下の2つを挙げる。
「まず考えられるのは、原材料が買えなくなるリスクです。
最近、オレンジ飲料の販売休止が相次いだニュースがありましたよね。原因は、最大の輸入先であるブラジルで天候不順や病害により、オレンジが不作になったからです。また、バナナも病害による不作が広がっています。
このように昨今、自然環境の変化によって原材料が不足するケースが増えていますが、欧州では10年前ほどからこういったリスクを鑑みて、複数産地からの調達を進めてきました。
私も当時から日本企業に提案していましたが、先手を打つことはできなかった。
今後も同じような認識なら、円安も相まって、さらに買い負けが進むと危惧しています」(足立氏)
他にも、海外で販売ができなくなるリスクもあると言う。
「今後は企業として生物多様性の保全に取り組んでいないと、市場が買ってくれなくなるでしょう。
欧州ではEUDR(EU Deforestation Regulation:欧州森林破壊防止規則)が発効され、大企業は2024年12月30日、中小企業は2025年6月30日から適用が始まります。
EUDRでは、製品に使われるパーム油、コーヒー、カカオ、牛、大豆、天然ゴムなどの原材料が森林を破壊していない証明を企業自ら行う必要があります。
その証明ができなければ、EU市場には輸出ができずに市場から締め出されてしまうわけですが、多くの日本企業はまだその対応ができていません」(足立氏)

こういったリスクを聞くと、生物多様性の保全への取り組みは企業にとって新たな負担だと感じてしまうかもしれない。
そのような懸念に対して足立氏は、「正しいリスク管理やスピーディーな対応を行えば、新たなビジネスチャンスになる」と話す。
その鍵を握るのが、前述したNbS (Nature-based Solutions:自然を活用した解決策)だ。
「"水害の防ぎ方"を例に考えてみましょう。これまでは水害を防ぐためにコンクリートで高い堤を作っていましたが、最近注目されているのは、コンクリートだけに頼るのではなく、緑地などで水害を防ぐ方法です。
グリーンインフラと呼ばれますが、これはまさにNbSで、"緑による防災技術"は大きなビジネスになるでしょう。
また、一次産業にもビジネスチャンスが広がっています。日本で一次産業といえば農林水産業で、古臭く儲からない産業というイメージがあるかもしれません。
しかし、世界に目を向けると一次産業は今や成長産業。それも、IoTを活用したスマート農業だけに傾倒せず、自然の力を活かした効率的で経済的、しかも環境を良くする農業が世界中で実践されています。
日本でも実践できれば、大きなビジネスチャンスになるはずです」(足立氏)

18世紀後半に起こった産業革命は、社会構造や人々の生活に大きな変化をもたらした。
以来、電気や石油をエネルギー源とする重化学工業の発展、原子力エネルギーの利用、デジタル革命と、産業は加速度的に発展を続け、一方で自然環境の破壊、生物多様性の喪失といった深刻な問題を引き起こしてきた。
ブループラネット賞の受賞が決まったIPBESは、「現状を放置し続けると、地球上の全動植物の8分の1ほどにあたる約100万種が、数十年以内に絶滅する可能性がある」と警鐘を鳴らす。
「恐竜の絶滅を始めとして、これまで地球では、隕石の衝突や気候変動などによって、5回の絶滅期があったと言われています。そして現在言われているのが、"第6の絶滅期"に入ったという説。
恐ろしいのは、これまでの絶滅期と比較して、絶滅の速度が圧倒的に速い(一定時間に絶滅する種の数が多い)ということです。
そういった問題に気づき始めたからこそ、サーキュラーエコノミーやカーボンニュートラルを目指そうという機運が高まっています。
後の人々から見ると、今この時代が、産業革命以来の大きな転換期になるのではないでしょうか」(足立氏)
そんな中で足立氏が期待するのは、日本のリーダーシップだ。
先進国内でも圧倒的に豊かな自然環境を持つ日本。「自然を上手く活用したビジネスを作ることができれば、環境分野で世界をリードできるはず。日本企業にはぜひ、その方向へと舵を切ってほしい」と話す。
企業にとって、生物多様性を守るための取り組みが遅れることはリスクになる一方で、正しい情報を得て、スピーディーに対応できればビジネスチャンスにもなる。
ここからの企業の動き方が、社会、ひいては地球の未来にとっても重要な一歩となるはずだ。まさに今、我々は大きな岐路に立っている。

Profile
足立直樹(あだち・なおき)氏
東京大学理学部、同大学院で生態学を学び、博士(理学)号取得。1995年から2002年までは国立環境研究所で熱帯林の研究に従事する。1999年から3年間のマレーシア森林研究所勤務の後、コンサルタントとして独立。現在はレスポンスアビリティ代表取締役、企業と生物多様性イニシアティブ(JBIB)事務局長など。企業による生物多様性の保全の推進に力を入れ、多くの先進企業の調達や経営をサステナブルにしてきた。現在は特に、自然を活用したビジネスの推進や地域を活性化することに注力する。新聞、雑誌、Webに掲載記事、寄稿文等多数。
Business Insider Japan掲載記事
ブループラネット賞について詳しくはこちら

